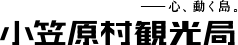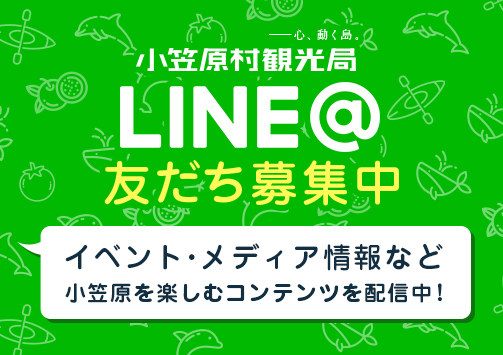小笠原は一度も他の陸地と繋がったことがない海洋島のため、独自の進化を遂げた生き物が生息しています。
世界自然遺産に登録される際の決め手となったのも、独自の生態系や固有種率の高さでした。
固有種は、世界中のごく一部でしか見られないもの、
今回は、母島に生息している生き物の一部をご紹介します。
生態系の頂点の生き物はこんな動物!
小笠原の生態系ですが、火山活動でできた海洋島のため、海を越えてくることが難しい大型の哺乳類は生息していません。
もともといる生き物の生態系の頂点の生き物は猛禽類の固有亜種オガサワラノスリです。
他地域のノスリに比べると体色がやや白っぽいといわれています。
母島では40~50羽くらいの頭数で、食べ物は外来種のネズミを多く食べています。
早朝に集落を散歩していると、電柱の上にとまっているオガサワラノスリに出会うこともあります。

天然記念物 オガサワラノスリ 撮影:梅野ひろみ
ニックネームはクロポッポ&アカポッポ
小笠原で10年前には40~50羽くらいしかいない幻の鳥といわれていたのがアカガシラカラスバトです。
ノネコ(森などで暮らしている野生化したネコ)の捕獲の成果があがり、頭数も増えてきて今では小笠原全体で600羽以上はいるのではないかといわれています。
小笠原では、アカガシラカラスバトに親しみやすいニックネームがついていて、幼鳥は体色が黒っぽいのでクロポッポ、成鳥になると頭部に赤みがでてくるのでアカポッポとよばれています。
アカポッポは、太陽の光を浴びると首~背中にかけての羽毛が玉虫色に輝いてほんとうに綺麗です。

天然記念物 アカガシラカラスバト 撮影:梅野ひろみ

天然記念物 アカガシラカラスバト 撮影:梅野ひろみ
種分化で仲間がとっても増えました!
小笠原の生き物を語るうえで欠かせないのが陸産貝類(カタツムリ)です。
もともとの祖先は流木などによって運ばれ、そこから小笠原の環境の中で適応放散と種分化(環境に応じて進化し、種類が分かれること)によってなんと100種類もの仲間に増えたそうです。
母島の標高が高い林内には、湿った環境の中で殻が小さくなるという進化を遂げたカタツムリがいます。
オカモノアラガイ科の2種類で、テンスジオカモノアラガイとオガサワラオカモノアラガイです。
少しだけ違いがありますが、分かるでしょうか?

天然記念物 テンスジオカモノアラガイ 撮影:梅野ひろみ

天然記念物 オガサワラオカモノアラガイ 撮影梅野ひろみ
その他にも、環境に適応してこんな色や形の生き物がいます。
地上性のカタツムリのヌノメカタマイマイは、落ち葉の表面のカビやコケ等を食べるそうで、体色も焦げ茶色です。

天然記念物 ヌノメカタマイマイ 撮影:梅野ひろみ
そして、樹上性のヒシカタマイマイは、植物の新芽等を食べているのではといわれていて、体色も樹皮の色に近い保護色です。

天然記念物 ヒシカタタマイマイ 撮影:梅野ひろみ
なかなか見ることが難しい昆虫類
亜熱帯の島というと、色も鮮やかな沢山の種類の昆虫がいるというイメージがあると思いますが、残念ながら小笠原では外来種のグリーンアノールの影響で昆虫が減ってしまいました。
そんな中で、秋頃から比較的観察しやすいのがオガサワラゼミです。
9月頃に母島の森ではオガサワラゼミの大合唱が聞かれます。
羽化したばかりのオガサワラゼミは、羽が透き通り体色も緑がかっていてとても美しい色をしています。

天然記念物 オガサワラゼミ 撮影:梅野ひろみ
そして、トンボ類やチョウ類は一年おきの旱魃の影響もあり、とても数が少なくなっています。

天然記念物 シマアカネ 撮影:梅野ひろみ

天然記念物 ハナダカトンボ 撮影:梅野ひろみ
いかがでしたか?
いかがだったでしょうか?
今回ご紹介したのはほんの一部ですが、固有種や固有亜種の生き物は多くが天然記念物で保護されている生き物なのです。
こうした生き物に接するときには、法律で保護されている絶滅危惧種だということを理解して、大事にして見守るようにして接してください。
ガイドツアーでもこれらを積極的に紹介するということはせず、ツアー中に出会ったときには観察しますが、どちらかというとこの生き物が生息する環境や生態についてのお話が中心になります。
ここにしかいない生き物は、ここでしか生きられない生き物です。
大切に見守っていきたいですね!

書いた人の他の記事
- カタツムリ
- バードウォッチング
- 固有亜種
- 固有種
- 昆虫
- 母島
関連記事

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#9523 (11) { ["term_id"]=> int(17) ["name"]=> string(6) "自然" ["slug"]=> string(6) "nature" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(17) ["taxonomy"]=> string(12) "archive_cate" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(49) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "3" } } 自然 - 2021.9.22
小笠原ビジターセンター特別展「オガサワラカワラヒワ展」
- オガサワラカワラヒワ
- ビジターセンター
- 固有種
- 母島
- 父島
- 観光施設

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#9543 (11) { ["term_id"]=> int(17) ["name"]=> string(6) "自然" ["slug"]=> string(6) "nature" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(17) ["taxonomy"]=> string(12) "archive_cate" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(49) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "3" } } 自然 - 2021.3.2
The deepest hahajima, SEKIMON
- トレッキング
- バードウォッチング
- 固有種
- 母島
- 絶滅危惧種

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#9549 (11) { ["term_id"]=> int(17) ["name"]=> string(6) "自然" ["slug"]=> string(6) "nature" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(17) ["taxonomy"]=> string(12) "archive_cate" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(49) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "3" } } 自然 - 2020.3.18
小笠原地域振興の新しい取り組みパート3 「製材」と「木工所」
- OEDC
- イベント
- 固有種
- 地域振興
- 外来種
- 持続可能

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#9536 (11) { ["term_id"]=> int(17) ["name"]=> string(6) "自然" ["slug"]=> string(6) "nature" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(17) ["taxonomy"]=> string(12) "archive_cate" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(49) ["filter"]=> string(3) "raw" ["term_order"]=> string(1) "3" } } 自然 - 2020.3.6
小笠原地域振興の新しい取り組みパート2 「生態系保全」と「林業振興」
- OEDC
- イベント
- 固有種
- 地域振興
- 外来種
- 植物